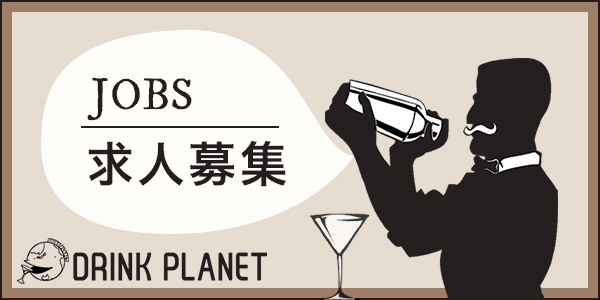⇒Englishx close

PICK UPピックアップ
隠し味は個性的な「人」!
ココ・ファームのおいしい秘密。
<後編>
#Pick up
醸造部長・柴田豊一郎さん&醸造スタッフ、栽培スタッフ from「ココ・ファーム・ワイナリー」
文:

山にトンネルを掘ってセラーを作った。一年を通じて温度変化があまりなく、適度な湿度もあり、ワインを寝かせるにうってつけの条件が揃った。
特別支援学級の課外活動からはじまり、国内のトップワイナリーにまで成長したココ・ファーム・ワイナリー。
前編で述べた通り、現在もこのワイナリーを支えているのは、指定障がい者支援施設「こころみ学園」の100人の園生と20数名のスタッフたちだ。
醸造所の前に広がる急斜面の畑では、滑り落ちないように脚を踏ん張って、
数名のスタッフと園生が剪定作業を行っていた。
「8時半に集まって、お昼の休憩をはさんで夕方5時まで作業。
夏は暑い、冬は寒い。春には花粉が飛来する。過酷です」
と笑う、畑のスタッフ島野さん。
ブドウの枝はみな、カーテンのように下向きに垂れ下がっている。
「ダブルカーテンというのですが、下向きにすることで枝がこれ以上伸びず
ブドウが結実に集中するので、よい実ができるんだそうです。
ブルースさんの知り合いの栽培コンサルタント、ドクター・スマートに教えてもらった技法です」
切り落としたブドウの枝は集めて、火にくべる。
恒例のお祭りで、よいブドウ、そしておいしいワインができるよう、
ブドウの守り神であるサン・ヴァンサンにお祈りするのだそうだ。
たる火から立ち上る白い煙には、剪定後のブドウの枝についた害虫や病原菌を焼き払う効果もあるのだとも。
「開墾以来、この畑に除草剤や殺虫剤、化学肥料などが使われたことはないんです」
と教えてくれたのは、ワイナリーの母体であるこころみ学園の理事会事務局長を務めている牛窪利恵子さん。

カフェの入り口には開墾当時の写真が飾られている。空き缶を持ち、カラスを追う「カラス番」の仕事風景。
「その時代ですから、オーガニックや有機栽培に着目していたわけではありません。
この施設はそうした肥料を買えるほど裕福ではなかったことが一つと、
園生たちが思いっきり身体を動かせるような、たくさんの作業を必要としていたこと。
草を刈る、虫を取る。
作業が多ければ多いほど、園生たちには都合がいい。
そうした作業で根気が養われるし、ブドウ収穫時には仕事への誇りが生まれます。
だから除草剤も殺虫剤も必要なかったんです」
できることはなるべく自分たちで行う。
ワイナリーのために始めたブドウ畑ではなく、子どもたちを育てるための畑だからこその地道な積み重ねが、おいしいワインを作る秘訣だった、というわけ。

カフェではワインにぴったりのメニューがサーブされる。こちらは日替わりのスープランチ(¥1,000)。まろやかで滋味深いきのこのシチュー。
ブドウ作りは土作りから始まり剪定、草刈り、鳥や虫除け、一房ごとの摘粒作業、収穫と手作業で行わなければならない。
夏の炎天下、あるいは「赤城のからっ風」が吹く寒い冬の一日、
戸外での作業はいかにもきつい労働だが、
そうした毎日の地道な作業が実を結び、
いつのまにかココ・ファーム・ワイナリーは日本でも屈指のワイナリーに成長した。
現在はココ・ファーム・ワイナリーの取締役であるブルースさんも
「ワインの出来は80~90パーセントはブドウの質できまる。
そのブドウを作っているのは園生たち。
園生がいたからこのワインができた」
と彼らの仕事ぶりを高く評価している。
剪定した枝を集める係り、ブドウにかさをかける係り、あるいは空き缶を叩いてカラスを追い払う係り。
何役もこなすことは出来ないけれど、自分の仕事は完璧に、誇りを持って遂行する。
ブドウ畑で、醸造所で、根気強く作業に勤しむ姿勢も粋な、たくさんの農夫たちに出会った。

園生とともに汗を流す、醸造&畑のスタッフたち。
「おいしいワインの秘密は?」と問えば、
ブドウや酵母が語る声に耳を傾け、その持ち味を活かすことが
ここでのワイン作りのありかただという。
だからブドウも農夫も、個性的でいい。
50年前、生徒とともに畑を切り拓いた、こころみ学園園長川田昇さんは言う。
「消えてなくなるものに、渾身の力を注げ。
ワインもひとたび飲んでしまえば、なくなってしまう。
だからこそ、真面目に、正直に、手抜きしないで作ること」
この言葉に、ワイン作りの極意とプロフェッショナルな農夫の心意気を生み出した、
おいしさの秘訣が現れている。
SHOP INFORMATION

|
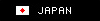 |
|---|---|
| ココ・ファーム・ワイナリー | |
|
326-0061 栃木県足利市田島町611 TEL:0284-42-1194 URL:http://www.cocowine.com |