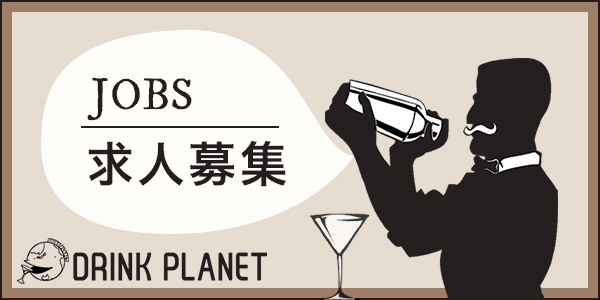SPECIAL FEATURE特別取材
【スペシャルレポート】
薬草酒マニアのバーテンダー鹿山博康氏、
アブサンの故郷、スイス・フランスをゆく。
[vol.01] -
魅惑のアブサン蒸留所めぐり!
<スイス編>
#Special Feature
文:Hiroyasu Kayama

左/スイスで出会ったアブサンファウンテンやアブサングラス。右/ニガヨモギに埋もれて至福の鹿山さん。
2016年の夏、新宿・西口にあるBar Ben Fiddichのオーナーバーテンダー鹿山博康さんが、スイス・フランスの旅に出る、という情報が入ってきました。
鹿山さんといえば、バー業界きっての薬草酒マニアであり、アブサン好き。
ついでにオールドボトルに目がなく、各種ボタニカルを自ら育てていることでも知られる人物。
Drink Planetで過去に鹿山さんを取材した記事はコチラ!
という訳で、せっかくなので今回で二度目だというアブサン蒸留所めぐりの旅を、鹿山さん自らレポートしてもらうことにしました。
では、ここからは鹿山さんのレポートとなります!

左より、鹿山さん、本坊酒造の田中さん、Bar Ben Fiddichスタッフの松沢さん。
皆さん、こんにちは。Bar Ben Fiddichオーナーの鹿山博康と申します。
今回のアブサンの旅は、本坊酒造の技師である田中智彦氏、当バーのスタッフ松沢健、そしてわたくし鹿山博康の三人で向かいました。
旅についてレポートする前に、日本ではまだまだマイナーな存在であるアブサンについて簡単に紹介させてください。
コニャックやシャンパーニュ同様、アブサンにも聖地と呼ぶべき有名な産地があります。
それが今回の旅の舞台でもある、フランスのフランシュ・コンテ地域圏のポンタルリエ(Pontarlier)から、国境を超えたスイスのヌーシャテル州ジュラ地方ヴァル・ド・トラヴェール(Val-de-Travers)。
この国境をまたいだエリアが、アブサン蒸留所がひしめき合っている地域です。
アブサンはもともと、スイスの山間部にある地域に根付いた滋養強壮の薬用酒。
(日本でいえば養命酒のようなもの!)
今を遡ること200年前、現在世界第2位の酒類メーカーであるペルノ・リカール社の創始者アンリ・ルイ・ペルノが、スイス山間部地域の薬用酒をフランスに持ち込み、ポンタルリエに一大工場をつくって量産しはじめたのです。
その後1830年代にフランスがアルジェリアに侵攻した際、水の衛生状態が悪かったために、兵士たちはアルコールであるアブサンの水割りを飲んでいました。
帰還後、英雄である帰還兵がフランス各地でアブサンを広めたことが、アブサンが流行るきっかけになったとされています。
また1860年代にフィロキセラの害虫でブドウの木が壊滅状態になると、アブサンがワインにとって代わったことも後押しとなりました。

アブサン発祥の地とされるクヴェ村。
しかし、19世紀末期から20世紀初頭、あまりにも流行り過ぎたアブサンに禁止令が出されます。
皆さんもご存じの通り、アブサンのメインボタニカルであるニガヨモギにあるツヨン成分が幻覚作用を引き起こすとされたのです。
確かに、ツヨンには幻覚作用はありますが、天文学的な量を摂取しないと幻覚は見えないということです。
では、なぜ禁止にまで追い込まれたのでしょうか?
これには3つの理由があります。
①19世紀半ば、フィロキセラの害虫で壊滅状態にあったワイン業界が19世紀末には復活。ワイン業界をさらに後押ししたかたったフランス政府は、アブサンには幻覚作用があるとプロパガンダした。
②粗悪な蒸留業者が工業用アルコールでカサ増しし、利益優先に走ったことで健康被害が続出(この時代に流行った蒸留酒にはよくあること)。
③1920年代のアメリカ禁酒法同様、酒は悪の風習を流布するとするヒステリックな団体の台頭。
これら3つの理由が重なり、スイスでは1910年、フランスでは1915年、アブサン製造が禁止されました。
そんな悲運の酒ですが、禁止後もフランシュ・コンテ地域およびスイス山間部のヴァル・ド・トラヴェールでは密かにアブサンが造り続けられました。

左上より時計回りに、Volote Martin蒸留所、Bovet蒸留所、試飲中の鹿山さん、Celle a Guilloud蒸留所。
では、話を旅に戻しましょう。
私自身2度目となるアブサン地域圏の旅はここスイスから。
ヴァル・ド・トラヴェール地方のアブサン発祥の地とされるクヴェ村です。
クヴェ村のアブサン生産者は、皆が皆、個人経営の小さな造り手ばかり。
ちなみにスコットランドのウィスキー製造における法規定の最小単式蒸留器の容量は2,000ℓとされていますが、ここスイスでは100ℓ前後が大多数です。
ヴァル・ド・トラヴェールでは登記されている蒸留所が約25あります。
ライセンスなしで製造している人(スイスでは個人蒸留は200ℓまで認められている)、あるいはレシピを委託して造ってもらっている人を含めると、現地の人にも正確な数はわからないとのことです。
ただひとつ言えることは、本業をアブサンだけに注力しているのはごく一部の蒸留所だけ。
ほとんどは兼業であり、役所に勤めながらアブサンを造っている人、大学の講師をやりながらアブサンを造っている人など、実にさまざまです。
そういったアブサンはスイス国内にしか出回ってないケースが圧倒的です。

エルボリステ蒸留所にて、造り手のピエール・アンドレさんとともに。
例えば、今回訪れたエルボリステ(Herboriste)蒸留所。
小屋のような小さな建物の中で、100ℓの蒸留器でアブサンを造るのは、ピエール・アンドレさん。
もともとは薬科大学の講師で、現在は奥さんとともに薬局を経営しています。
その傍ら、アブサンを造っているのです。
エルボリステ蒸留所のアブサンは、なんとピエールさんの薬局にしか売っていません!
にもかかわらず、彼の元には世界中からバイヤーやアブサン好きが訪れます。
(アブサンが解禁されてから10年以上を経て、以前よりもアブサン目的でヴァル・ド・トラヴェール訪れる人が増えているんだとか)
先日もアメリカから毎月15本を送ってほしいとの依頼がきましたが、ピエールさんは断わったそうです。
「なぜ断わったの? もったいない」と質問したら、「金持ちになりたいわけじゃないから」と一蹴されました。
何にも縛られず、個人レベルで自由に納得いくスタイルでアブサンをつくる……。
私もそうした世界観に憧れます。
本来アブサンとは、こういうものなのかもしれません。
vol.02へつづく。