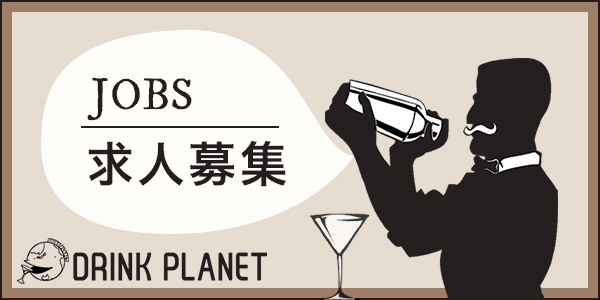PICK UPピックアップ
タイトルなしから世界No.1へ!
ワールドクラスの勝ち方とは!?
<後編>
#Pick up
金子道人さん from「LAMP BAR」
文:Drink Planet編集部

「ワールドクラス」の栄誉あるチャンピオンシェイカー。
金子さんが「ワールドクラス ジャパンファイナル」を制し、日本代表の座を射止めたのは2015年6月1日。
その後、グローバルの大会本部からチャレンジマニュアルが届いたのは、世界大会まで1カ月に迫った7月後半のことだった。
しかもレシピ提出期限は8月14日。
各チャレンジの内容を理解し、その意図を解釈しながら、オリジナルレシピを組み立てるのにわずか2週間しかない。
さらに、前年までは限られたチャレンジのみレシピ提出が求められたが、2015年からは即興系のもの以外はすべてのチャレンジにおいてレシピ提出が義務付けられた。
(トップ6名しか参戦できないファイナルチャレンジ“Cape Town Shakedown”も含む!)
「2週間という期間はもちろんですが、夏休みの忙しい時期でもあったので、『グローバルファイナル』の大会自体よりも、このレシピ提出のほうがキツかったくらいです」

“Night & Day”チャレンジで創作したナイトカクテル「From 23」。
レシピ提出や世界大会に向けて、奈良の先輩であり、「ワールドクラス」日本チャンピオンである渡邊匠さんや宮﨑剛志さんからはアドバイスがあったのだろうか?
「はい、お二人には本当にお世話になりました。渡邉さんは具体的なアドバイスというよりも、精神的に支えてもらった感じです。『気にせずやってこい』みたいな言葉をいつもかけてくれました。渡邉さんのお店は同じ奈良でも少し離れた場所にあるのですが、お店が終わった後に、わざわざ自宅を通り越して、私の店までたびたび足を運んでくれました」
「宮﨑さんには味覚の部分で的確なアドバイスをもらいました。2013年に世界大会を経験しているし、奈良にいても世界のバーシーンを肌で知っている方なので、大変心強かったですね。2011年の世界チャンピオンである大竹さんにも事前に声をかけてもらったし、現地の南アフリカでもいろいろとサポートしてもらいました」
通算7回の「ワールドクラス」で、日本から世界チャンピオンが2人も誕生した理由は、日本人バーテンダー同志の強い絆によるところも大きいのかもしれない。
その他、具体的にどんな練習を重ねたのだろうか?
「プレゼンテーションの練習する際は、絶対に1人ではやらない、と決めていました。必ずだれか見てくれる人がいる前で練習するようにしました。『Bar OLD TIME』の後輩バーテンダーだったり、近所のバリスタの方だったり、まったく飲食経験のない知り合いの方だったり、とにかく周囲の方々が時間を割いて僕の練習に付き合ってくれたんです」
周囲にいる人々をことごとく味方につけてしまうのも、金子さんの人柄であり、バーテンダーとしての資質のひとつなのだろう。
こうして忙しいなかでもきっちりと準備を進め、普段の営業から練習を積み重ね、世界を意識してきた金子さんだからこそ、世界の大舞台でもいい意味で開き直れたに違いない。

「ワールドクラス グローバルファイナル 2015」に参戦した54ヵ国54名のバーテンダーたち。
パフォーマンスという意味で、英語への不安はなかったのだろうか?
「チャレンジはすべて日本語で行いました。もちろん英語が喋れたらベストですが、普段のバーテンディングをきっちり見てくれるのが『ワールドクラス』。僕が優勝できたことでも、英語の能力ではなく、バーテンディングを評価してくれていることが証明されたのではないでしょうか。通訳の方やサポートしてくれたチームジャパンの方々に本当に感謝しています」
とはいえ、コミュニケーションは欠かせないはず。
「はい、もちろん英語が喋れないなりにコミュニケーションは取りました。臆せず、ひるまず、自然体で、常ににこやかにしているように心がけました。店に言葉が通じないお客さまがいらっしゃった時にも、表情や身振り手振りでコミュニケーションは取れますから……。『ワールドクラス』はその延長、くらいに考えていました」
ジャッジの一人、マエストロことサルヴァトーレ・カラブレーゼ氏も「言葉は通じなくてもいい。表情や振る舞い、接し方だけでも伝わるものは伝わる」と語っていたそうだ。
最近では中南米やアジアなど、非英語圏からの挑戦者も増えた。
そういう意味でも、「ワールドクラス」は世界に開かれた、誰にでもチャンスがある大会といえるだろう。

“Street Food Jam”チャレンジではジャッジをうまく巻き込みながらカクテルを創作した。
金子さんの中で最も手ごたえを感じたチャレンジは、前編でも述べた最初の“Against the Clock”チャレンジだったそう。
ここで一気に波に乗れたことは大きい。
「スピード系のチャレンジは練習が結果に直結します。逆にいうと、練習すればするだけ結果がついてきます」
「日本では、わざと途中で失敗してから、それをリカバリーする練習を重ねてきました。あとはあえて狭いカウンターで練習したり、逆に広いスペースで練習したり……。身体に染み込ませるだけでなく、頭にもレシピやオペレーションを叩き込んで、いわばアクセルとブレーキの使い分けの判断を磨いてきました」
実際、今大会のカウンターは想像以上に使いにくかったそう。
おまけに手から出血するというトラブルがあったものの、それも想定の範囲内だったわけだ。
また“Street Food Jam”チャレンジをうまく切り抜けられたことも大きかったという。
同チャレンジは、当日明かされる南アフリカ料理2皿に合わせて、限られた材料でカクテル2杯を創作するもの。
実は毎年、この即興系のチャレンジで大コケしてしまう有力選手が多い。
金子さんはどんな対策を練っていたのだろうか?
「日本で一度南アフリカ料理を食べに行き、スパイスの使い方などは前もってイメージしておきました。あとは料理の得意な後輩が、突然南アフリカをイメージした料理を持って店にやってくる。それに対してカクテルを創作する、というような練習もしました」
「もともと個人的にも料理が好きで、カクテルのロジックは料理から持ってくることが多いんです。レシピを開発する際、料理人の知り合いに相談することもしょっちゅう。そういういろんな要素が、うまくこのチャレンジに繋がったような気がします」
5つのチャレンジを終えた時点で「大きなミスもなく、自分の中でやりきった感があった」という金子さんは、見事トップ6に選出され、ファイナルチャレンジへと進んだ。

ファイナルチャレンジ“Cape Town Shakedown”でつくり上げたマイバー。
ファイナルチャレンジ“Cape Town Shakedown”は、自分のバーを立ち上げるというチャレンジ。
限られた予算の中で、自らのバーコンセプトをデザイナーに伝え、市内のインテリアショップで調度品を購入(レンタル)し、特設会場内にマイバーをつくる。
そこで、コンセプトに沿ったオリジナルカクテルを提供するのだ。
「もちろんチャレンジ内容は聞かされていましたが、正直、現場ではなにから始めていいのかわからないことだらけでした。デザイナーさんに何度もコンセプトを伝え、インテリアショップにも足を運びましたが、どんなバーになるのか不安でたまりませんでした」
「結果、できあがったバーは自分のイメージとはまったく違っていたんです(笑)。でも、コンセプトはしっかり練ってあったし、カクテルに対する準備もきっちりしてきた。そこにブレはありませんでした。ですから、ここでも“まあ、いっか”とうまく開き直れました」
金子さんは自らの“道人(Man on the Road)”という名前と、ジョニー・ウォーカーの象徴である「ストライディングマン(闊歩する英国紳士)」から、コンセプトを「The Travelling Bar Man」とした。
自らのバーを訪れるゲストに向けて、スコットランドからフランスを経由し、日本へと旅する、いわば“カクテル旅行”をプレゼンテーションした。
そしてその夜、世界一の栄光をつかみ取ったのだ。
世界一となり、金子さんはひとりの日本人バーテンダーとして何を思ったのだろうか?
「ジャパニーズバーテンディングの所作、清潔感、テクニック、一人ひとりのゲストをきちんともてなそうとする姿勢は、世界でも十分に通用するし、それ以上に世界の人々を感動させられるんだ、と痛感しました」
世界チャンピオンとして、今後の展望はどうだろうか?
「まだ実は何をどうしていいか自分でもわかっていないんです(笑)。具体的に決まっていることもありません。ただ『ワールドクラス』の世界チャンピオンになった以上、日本の諸先輩方が長い年月をかけて培ってきたジャパニーズバーテンディングを、世界にしっかり伝えていくことが今後の僕の役目だと考えています」
最後にズバリ「ワールドクラス」で優勝するには?
「僕は人生でコンクールやコンペティションと呼ばれるものにたくさん出場してきましたが、2回しか勝ったことがないんです。1回が今年の『ワールドクラス ジャパンファイナル』。そしてもう1回がこの『グローバルファイナル』。戦績でいったら2勝100敗くらい(笑)。ですから、とにかくチャレンジし続けることではないでしょうか。僕に言えるのはそれくらいしかありません」
コンペティションでの受賞歴なし、しかも地方で小さなバーを切り盛りするバーテンダーが一気に世界のスターダムへ。
だから「ワールドクラス」はおもしろい!
SHOP INFORMATION

|
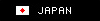 |
|---|---|
| LAMP BAR | |
|
630-8224 奈良県奈良市角振町26 いせやビル 1F TEL:0742-24-2200 |